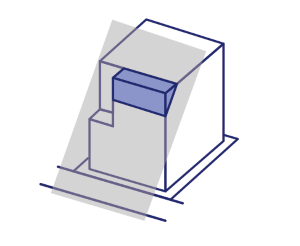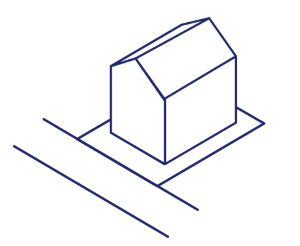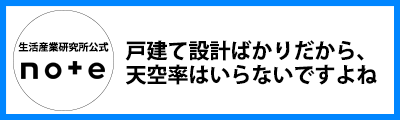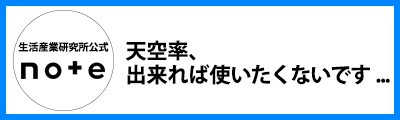天空率について
設計の自由度を上げる天空率
天空率は、設計者にとって様々なメリットをもたらします。 天空率を使いこなして建築設計をもっと自由に行いましょう。
【天空率制度を利用するメリット】
- 斜線制限の緩和
- 使用容積率のアップ
- 構造体への負担減
- 建築可能空間の創出
- 採光の確保
- 庭(空き地)の有効利用
- 他社との差別化
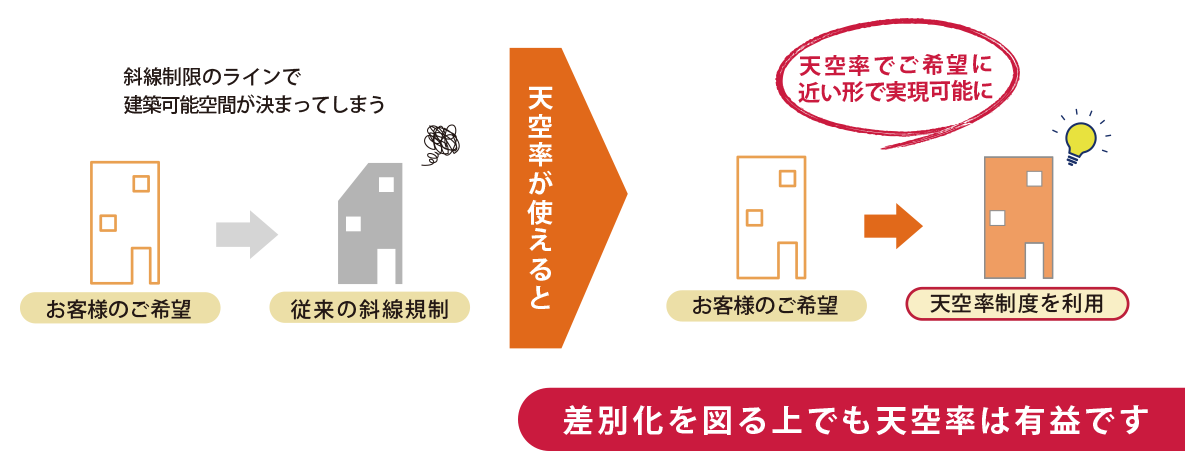
■天空率の申請について
天空率 ( 建基法第 56 条 7 項 ) を利用する場合は、確認申請図書に算定結果等の提出が求められます。申請図に関しての資料がダウロードできます。
○天空率申請図の手引書
○天空率算定申請図書サンプル
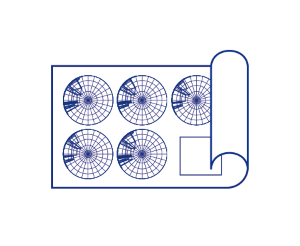
■フリーCADソフトと有償ソフトでの天空率計算操作の比較
操作方法の一例ですが、天空率計算におけるフリーCADソフトを使った場合と、専用ソフト(ADS)を使用した場合の作業の流れを比較してみました。
タイムパフォーマンスが重視される昨今、何に注力するかの参考にしていただければ幸いです。
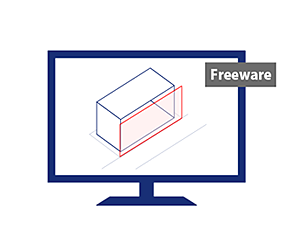
■作業効率で比較する天空率計算
天空率計算システムのフリー版と有償版の違いについて、「手動」で行うか「自動」で生成するかによってシミレーションの時間に大きな差が出ます。
人手が足りない問題も、システムの導入で解決する場合も。

生活産業研究所公式 note記事
天空率についてもっと学びたい方へ
セミナーの受講で理解をさらに深める
天空率解析ソフト ADS で天空率計算を体験
天空率解析請負サービス
天空率についてのご相談(無償 / 有償)
関連条文
天空率関連条文
建築物の各部分の高さ(基準法第56条 ▶)
高さ制限を適用しない建築物の基準(施行令 第135の6~8 ▶)
天空率の算定位置(施行令 第135の9~11 ▶)
道路斜線提要距離及び勾配(基準法 別表第3 ▶)
その他関連条文
容積率(基準法第52条 ▶)
建蔽率(基準法第53条 ▶)
敷地面積(基準法第53条の2 ▶)
日影規制の制限(基準法 別表第4 ▶)
天空率公開情報
【JCBA】天空率の運用の検討について(2010年4月20日)
「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」について(日本建築行政審議会 PDF ▶)
【JCBA】天空率の運用の検討について(2009年5月18日)
「天空率運用の検討について」平成20年度の活動報告書(日本建築行政審議会 PDF ▶)
改正建築基準法情報(2007年6月20日)
平成19年6月20日施行の改正建築基準法等について(国土交通省サイト ▶)
※詳細は、各行政庁及び民間確認検査機関にてご確認ください。
まちづくりNPO「天空の会」
天空率制度・計画手法の普及を目指す特定非営利活動法人

(NPO法人 天空の会サイト ▶)
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます